- 再発転移がん治療情報
- がんを見つける・予防する あきらめない「予防医療」
- がんを見つける
- 【特集記事】予防医療の専門医に聞く。「がん検診の正しい選び方」
【特集記事】予防医療の専門医に聞く。「がん検診の正しい選び方」
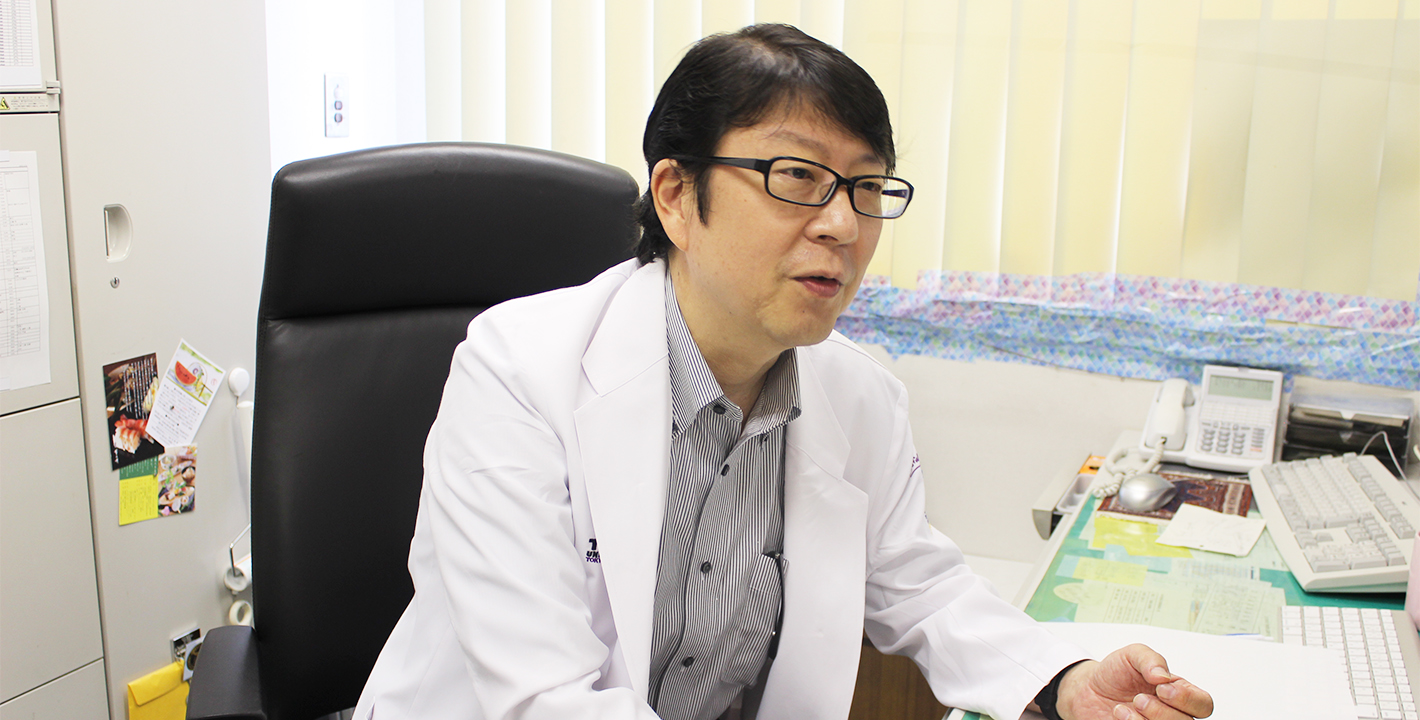
西崎 泰弘(にしざき やすひろ)先生
現在、日本人男性の2人に1人、女性の5人に2人が罹患するといわれるがん。早期発見には「がん検診」が有用ですが、いざ受けようと思っても、検診の種類・費用・時間など、よくわからず不安に感じる点もあるでしょう。
そこで、東海大学医学部付属東京病院で病院長・健診センター長を務める西崎泰弘先生に、がん検診の基礎知識や選ぶポイント、ご自身が受けているがん検診などについてお伺いしました。
目次
死因トップにもかかわらず、依然低いがん検診受診率

日本人の死因第1位はなにかご存じでしょうか。答えはがん(悪性新生物)です。全死亡者に占める割合は27.4%で、およそ3.6人に1人ががんで亡くなっていることになります※1。1980年までのおよそ30年間は、脳卒中(脳血管疾患)が死因の第1位でしたが、1981年以降から現在までは、がんが死因のトップとなっています。
そもそもがんとはどのようにして生じるのでしょうか。
人間をはじめとした動物は、日々細胞が入れ替わりながら生きていますが、実は、そのサイクルの中で毎日いくつもの“細胞の出来損ない”ができており、これががんの原因になります。
通常は、体内の免疫を担当する細胞がこの“出来損ない細胞”を排除してくれるのですが、加齢などにより免疫力が低下し、免疫細胞が排除しきれなくなると、出来損ない細胞が増殖し、やがて“がん”となります。
つまり“がん”とは、もともと体の中にあった正常な細胞から生じたもので、誰でも発症する可能性があると言えます。2007年に超高齢社会となった日本で、がんが死因の第1位というのは当然とも言え、今後もこの状況は大きく変わらないでしょう。
このような背景の中、国は2007年に「がん対策推進基本計画」を策定し、がん予防の充実と早期発見・早期治療につながるがん検診率向上などを掲げました。具体的にはがん検診受診率を50%以上に引き上げることなどを目標にしています。
しかし、2016年のがん検診受診率を見てみると、40~69歳の男性の胃がん、肺がん、大腸がんの検診受診率は4〜5割程度、女性はその三つに乳がん、子宮頸がんを含めた五つのがん検診の受診率が3〜4割台にとどまっているのが実情です(子宮頸がん検診のみ20~69歳が対象)※2。

諸外国と比べても、例えばアメリカやイギリスでは乳がん検診と子宮がん検診の受診率が80%前後なのに対し、日本ではその半分の40%程度と低率です※3。
特に、健康保険組合連合会に属している健保組合に加入する企業の社員などの受診率に比べて、自営業や非正規雇用労働者、専業主婦・主夫の受診率が顕著に低いことは問題です※4。
※1 平成30年(2018)人口動態統計月報年計(概数)
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/dl/h6.pdf)
※2 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
(https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/screening.html)
※3 国立がん研究センターがん情報サービス
(https://ganjoho.jp/med_pro/pre_scr/screening/screening.html)
※4 平成30年度 東京都がん予防・検診等実態調査
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/gan/toukei/jittaityousa30.html)
二つの「けんしん」――「健診」と「検診」の違い

そもそも、「けんしん」とはなんでしょうか。「けんしん」には「健診」と「検診」の二つがあります。「健診」は「主に将来の疾患のリスクを確認する検査群」とされています。例えば、メタボリックシンドロームの予防と改善を目的とした特定健康診査(メタボ健診)などが該当します。
もう一方の「検診」は「主に現在の疾患自体を確認する検査群」とされます。すなわち「がん検診」は「いま、がんにかかっているかどうか」を確認するために行うものです。これによってがんを早期に発見できれば、迅速に適切な治療につなげることが可能となり、がんで死亡する人を減らすことができるとても重要な検査です。
国としても、日本の平和と安全を維持するためには国民の健康が不可欠ですので、厚生労働省は「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」を定め、がんの予防や検診の促進を積極的に取り組んでいます。
がん検診の選び方――「遺伝性のがんは任意型検診」の受診を
がん検診には、大きく分けて「対策型検診」と「任意型検診」の2種類があります。
「対策型検診」は、市区町村が「住民検診」として健康増進事業で行っているものです。具体的には、特にリスクが高いがんに対して、検診によって死亡率が下がると科学的に証明された五つの検診(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん)を、無料またはそれぞれ500~1,500円程度のわずかな自己負担で受けられるものです。
「任意型検診」は、個人が任意で受ける検診サービスです。人間ドック健診に代表され、対策型検診で受けられる基本的な項目だけでなく、対策型検診に含まれない、例えば前立腺がんのPSA検査のような、広範囲かつ精密な検査が受けられるのが特徴です。
各自が気になったり、身内が患ったので気をつけたいと考えたりする、部位ごとの検診を自由に選べるものです。こちらは対策型検診のように公共施策で行う検査ではないため、基本的には自己負担となりますが、所属する健康保険組合などによっては一部補助金が出る場合もあります。
下記に、それぞれの検診の特徴をまとめたので、自分のニーズに合わせて検診を選びましょう。
対策型検診と任意型検診
| 対策型検診 | 任意型検診 | |
|---|---|---|
| 目的 | ある集団(市区町村など)全体の死亡率を下げる | 個人が自分の死亡リスクを下げる |
| 概要 | 予防対策として行われる公共的な医療サービス | 医療機関・検診機関などが任意で提供する医療サービス |
| 検診例 | 住民検診 | 人間ドック |
| 受けられる 検診の種類 |
胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん | 医療機関・検診機関が提供するものから任意で選択 |
| 受診対象者 | 一定の年齢範囲の住民など、特定の構成員全員 | 定義されない |
| 検査費用 | 公的な補助金があるため無料または低額 | 自己負担(所属する健康保険組合などから補助金が出る場合もある) |
| 受診頻度 | 2年に1回または1年に1回(がん検診の種類によって異なる) | 1年に1回を推奨 |
| 受診場所数 | がん検診の種類ごとに異なる医療機関を訪れる場合もある | 1カ所 |
| 所要時間 | 五つの検診それぞれが10~15分程度 | 半日~1日程度(メタボ健診などがん以外の検査も含む) |
がん検診を選ぶ際は、血縁者のがん経験有無もポイントになります。遺伝が関係することがわかっているがん(大腸がん、乳がん、子宮体がん、すい臓がん)の経験者が血縁にいる方は特に留意していただきたいです。中でも、子宮体がん、すい臓がんは対策型検診に含まれないので、該当する方は任意型検診で定期的に検査することをお勧めします。
なお、遺伝するがんは全体の5%未満とされ、ほとんどのがんは遺伝とは関係ないと言われています。ですから、血縁者に上記の四つ(大腸がん、乳がん、子宮体がん、すい臓がん)のがん患者がいるからといって、過度に心配する必要はないことを付け加えておきます。
任意型検診を受ける場合も、対策型検診で受けられる五大がん(胃がん、肺がん、大腸が、乳がん、子宮頸がん)を優先しましょう。女性は5種、男性は3種なので、男性では前立腺がんの検査であるPSA検査をぜひ追加してもらいたいです。
また、胃がん、肝臓がんは、それぞれピロリ菌、B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスに感染していなければ発症リスクは低くなります。いずれも医療機関で検査することができるので、必要に応じて、がん検診とは別にこれらの感染有無を確認しておくとよいでしょう。
対策型検診で受けられる五つのがん検診
国が推奨するがん検診「対策型検診」で受けられる五つの検診についての特徴を下記にまとめました。対象年齢ごとに、男性は胃がん、肺がん、大腸がんの三つの検診を、女性はそれに乳がんと子宮頸がんの検診を加えた五つの検診を定期的に受けることが推奨されています。
加齢とともにがんのリスクは高まりますから、最低限これらの検診は活用するようにしましょう。
対策型検診として行われている五つのがん検診
| 種類 | 検査内容 | 対象者 | 受診間隔 |
|---|---|---|---|
| 胃がん検診 | 問診及び胃部エックス線検査(バリウム)または胃内視鏡検査 | 50歳以上 (※5) |
2年に1回 (※6) |
| 肺がん検診 | 問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診(数日かけて繰り返し痰を採って検査する。50歳以上かつ〔一日のタバコの本数×喫煙年数=600以上〕の場合に行う) | 40歳以上 | 年1回 |
| 大腸がん検診 | 問診及び便潜血検査(自宅で採取した便を検査する) | 40歳以上 | 年1回 |
| 乳がん検診 | 問診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ) | 40歳以上 | 2年に1回 |
| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診(ブラシなどで子宮頸部をこすって細胞を採取する)及び内診 | 20歳以上 | 2年に1回 |
出典:西崎泰弘.『月刊臨牀と研究』第96巻第8号.大道学舘出版部,2019,126p
※5 胃部エックス線検査については、40歳以上に対し実施可
※6 胃部エックス線検査については、年1回実施可
「人間の身体」と「がん」に関する基本的な知識を持ってほしい
最後に、この機会にぜひ、みなさんに知っておいてもらいたいことについてお話しします。決して難しい話ではありません。
まずは、人間の身体の基本的なことを知ってもらいたいです。「すい臓がん」と聞いてもすい臓がどこにあるのかわからない、同様に「大腸がん」でも大腸はどこからどこまでの臓器でどんな働きをしているのか知らないという方が意外と多くいます。
また、「がん」が死につながる病気であることは知っていても、まだがんになっていない方は“自分事”としてとらえられていないように感じます。
しかし、いまや「がん」は一生のうち2人に1人がかかり、3人に1人が亡くなると言われるほど身近な病気です。ご自身だけでなく、ご家族やご友人ががんにかかる可能性もあります。
がんの種類のことはもちろん、がんの進行度に応じた5段階のステージ分類があることや、再発や転移を起こすこと、検査や治療法にもさまざまな種類があることなど、がんの基礎知識をしっかり身につけて、“他人事”ではなく“自分のことだ”と理解してほしいです。
また、がんは早期に発見し、早期に治療を行えば、治る可能性がグッと高まります。 がん検診を受けて異常が見つかり「要精密検査」と言われても、基本的ながんの知識が不十分なばかりに必要性・重要性がわからず、「忙しいから」と精密検査をなかなか受けようとしない方もいます。
ご自身の身体やがんのことについてもっと関心を持って知識を備え、正しくがん検診を受けてもらいたいです。
私が受けているがん検診
ところで、医師である私が自身のがん検診を一体どうしているのか、気になる読者もいらっしゃると思うのでお話しします。
私は健康管理の一環で、2年に一度、胃と大腸の検査をまとめて行っています。これまでの検査で私にはピロリ菌はいないことがわかっており、胃がんのリスクは低いと考えられるのでこのくらいの頻度で検査すれば大丈夫だと判断しています。
また、半年に1回程度は自分で採血して、生活習慣病や腫瘍マーカー(主に血液中で測定できる、がんがつくり出す特殊な物質)を調べていますし、もちろん職場の検診もきちんと受診しています。
がんは進行するまで症状を出しません。そして症状が出たとき、それは絶対に早期のがんではないのです。みなさんも、各々の検査で推奨されている間隔でがん検診を受け、早期発見・早期治療を心がけていただきたいと思います。
ポイントまとめ
- 日本人の2人に1人ががんに罹患する一方、がん検診受診率は3~5割程度にとどまる
- がん検診は「がんを早期に発見し、迅速に適切な治療へつなげること」を目的としている
- がん検診には、国が推奨する五つのがんについて調べる「対策型検診」と、個人が自由に選んだ検診をまとめて受けられる「任意型検診」がある
- がんは他人事ではなく自分事と理解し、「人間の身体のこと」「がんのこと」に関心を持って、正しくがん検診を受けてもらいたい
取材にご協力いただいたドクター

西崎 泰弘 (にしざき やすひろ) 先生
東海大学医学部付属東京病院病 院長 /東海大学医学部付属東京病院病院 健診センター長
コラム:精密検査って必要なの?
前述のとおり、「検診」は「病気にかかっているかどうか」を確認することが目的なので、一つの検査で病気(がん)の疑いが判明した場合は、異なる方法でさらに詳細な検査を行い、病気の有無を確認します。この検査を「精密検査」といいます。ちなみに「再検査」は、同じ検査を行うことです。
精密検査の必要があるのに受けなかった場合、せっかくがん検診を受けたのに「がんにかかっているかどうか」をきちんと確認しなかったことになります。精密検査を受けなければ、早期発見できるチャンスを逃し、がんが転移などしてしまう可能性が高まります。のちのち後悔しないためにも、「要精密検査」の結果が出た場合は、必ず検査を受けるようにしましょう。
•がん検診の流れ

※参考:国立がん研究センター がん情報サービスより






