- 再発転移がん治療情報
- 家族と社会のがん闘病サポート
- がん患者さんの支援・サービス
- がんサバイバーシップ研究成果発表。
キーワードは「腸内細菌」「がん教育」「次のステージ」
がんサバイバーシップ研究成果発表。
キーワードは「腸内細菌」「がん教育」「次のステージ」

厚生労働省が2014年度から進めている「がん研究10か年戦略」や、2017年度からの「第3期がん対策推進基本計画」に、がんサバイバーシップの研究や支援の推進が盛り込まれるなど、「がんサバイバーシップ」が注目されています。がんサバイバーシップとは、がんの診断を受けた人(がんサバイバー)が治療後の生活の中で抱えるさまざまな課題を、社会全体で協力して乗り越えていこうという考え方です。公益財団法人がん研究振興財団はこの活動を支援するため、2015年度から「がんサバイバーシップ研究支援事業」を実施し、毎年、がんサバイバーに有益な研究成果を発表しています。2020年2月6日に行われた2019年度がんサバイバーシップ研究成果発表会・セミナーの発表から、特に注目の内容をご紹介します。
目次
がん再発の不安感に腸内細菌が関与。
不安や恐怖を和らげる栄養補助食品の開発も検討
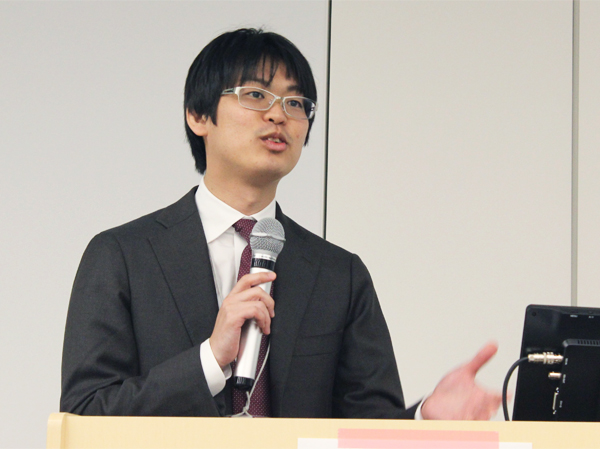
国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナル・メディカルセンターの
大久保 亮(おおくぼ りょう)先生
国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナル・メディカルセンターの大久保亮先生は「必須脂肪酸・腸内細菌叢バランスとがん再発不安の関連:探索的横断研究」をテーマに発表しました。
「がんサバイバーの79%が再発の不安を体験し、その内の7%では非常に強い不安感を抱えているといいます。そのような人は周囲からのフォローを避け閉じこもりがちになり、QOL(生活の質)や社会的な活動の低下を引き起こしてしまいがちです。」(大久保先生:以下同)
大久保先生は世界で初めて、がん再発に対する不安感に必須脂肪酸※1・腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)※2のバランスが関連することに着目して研究を実施しました。
その結果、えごま油や亜麻仁(あまに)油、くるみに多く含まれるアミノ酸の一種である「ALA(あら)」と呼ばれる成分の血中濃度が高いほど、がん再発に対する不安感が低いということが分かりました。
ALAは不安や恐怖に関する記憶の処理を促進する作用がある、という報告もあり、その作用が影響した可能性があるといいます。
さらに、大久保先生は「化学療法の影響で腸内細菌叢のバランスが変化し、最終的にがん再発に対する不安感に影響した可能性も示唆されました」と述べています。
これを受け、大久保先生が所属する国立精神・神経医療研究センターでは、がん患者さんの再発に対する不安感をやわらげる栄養補助食品開発の検討を開始したといいます。実現すれば、がんサバイバーが再発に関して、必要以上に不安を抱えることなく暮らせるようになるかもしれません。
※1 脂質を構成し、人間の細胞を作るのに必要な成分である脂肪酸の一種
※2 細菌が腸内で形成する菌種ごとのかたまり。植物が群生している花畑のような見た目であることから「腸内フローラ」とも呼ばれる
がんサバイバーの恋愛・結婚を教育で支える。
がんに対する偏見をなくすプログラムを開発

筑波大学大学院人間系・松井 豊(まつい ゆたか)名誉教授
筑波大学大学院人間系の松井豊名誉教授は「がん及びがん体験者への偏見に対する研修プログラム作成の試み―がんと恋愛・結婚に着目して―」をテーマに発表。がんサバイバーが抱える恋愛・結婚に関する問題点と、その解決策として大学教育を通してできることを提示しました。
がんサバイバーは、一般の集団と比べて婚姻率が低い傾向にあることが国内外の調査で分かっています。がん罹患歴があることや、治療が原因で外見や、妊娠のしやすさである妊孕性(にんようせい)に影響が出る場合があることなどを理由に、相手から交際や結婚を断られるケースが少なくないといいます。
がんサバイバーが抱えがちな悩みの一つとして「パートナーにいつ・どのように、がんであることを伝えればよいのか」ということがあります。
松井先生はその原因を「『がん』という言葉から、すぐ『死』を連想するなど一般人のがんに対する理解不足がある」と考え、がんに対する誤解や偏見を解消する教育プログラムの開発に着手しました。
恋愛・結婚への関心が高い未婚の若年層、特に大学生の男女を対象とし、実際に大学の授業でプログラムを試行して受講者の意識変化の調査を実施。
授業ではがん医療に関わる医師が、がんと妊孕性の関係やがんの遺伝などについて講義を行った後、がんサバイバーの20代男性が自身のがん体験談を語るという2部構成で実施しました。
そして、授業前後で参加者にアンケート(「1.そう思わない」~「5.そう思う」までの5段階評価)を取り、各項目の平均値を比較しました。
すると、
「(パートナーの)がんが再発・転移していたら交際を迷う」
「若くしてがんになった人はかわいそうだと思う」
「『がん』という言葉を聞くと、『死』を連想する」
といった項目で、実施後の評価平均値が下がり(「そう思わない」と答える人の割合が増加)、
「がんになると、子どもが持てなくなる」
の項目では評価平均値が上がる(「そう思う」と答える人の割合が増加)という結果となりました。
これは、がんという病気そのものや、妊孕性にどのように影響するかなどについて、正しい知識を得た結果であると松井先生は考察しています。
松井先生は今回の授業に手応えを感じ、今後はさらに以下の点を改善していくとのことです。
- ①講師の違いによる教育効果のばらつきを抑制する
- ②医療従事者や患者会などと連携し、教育用資料などの開発、教育プログラムの標準化、教育効果の評価の蓄積を進める など
今後も教育プログラムを見直し、「受講者が自分自身や身近な人が罹患する可能性があることを、現実問題として実感できる授業にしたい」と話しています。
ほかのがんサバイバーや医療者を支え、
元の生活からさらに「次のステージ」へ

京都大学大学院医学研究科・田村恵子(たむら けいこ)教授
後半の「がんサバイバーシップセミナー」では、がん看護専門看護師の田村恵子教授(京都大学大学院医学研究科)が登壇し、がんサバイバーを支援する立場から『ケア提供者としてがんサバイバーを支えるということ」をテーマに講演しました。その中で、がんサバイバーシップのあり方について以下のように説明しました。
「がんサバイバーの多くは『元の生活に戻りたい』と考えますが、がんサバイバーシップの考え方は違います。私たちが目指しているのは『元の生活のさらに次のステージに進むこと』です」
田村先生は、わが国の末期がんにおけるホスピスケア(緩和ケア)の草分けである大阪・淀川キリスト教病院で27年間勤務されるなど、これまで多数のがんサバイバーと交流を重ねてきました。
その経験を通じて気づいたのは、多くのがんサバイバーが『これからも人の役に立ちたい」という強い思いを持っていること。実際に、がんサバイバーのためのアロマセラピーなど、がんサバイバーががんサバイバーのためにイベントや企画などを行う人も少なくないといいます。
「がんサバイバー一人ひとりが、誰かを支える力を持っていると私は考えます。現在、がん罹患者、すなわちがんサバイバーが増えています。こうした社会におけるがんサバイバーが次のステージで果たす役割とは、ほかのサバイバーや医療者を支えることなのではないでしょうか」と、田村先生は締めくくりました。
ポイントまとめ
- 公益財団法人がん研究振興財団主催の「がんサバイバーシップ研究支援事業」では、がんサバイバーシップにとって有益な研究を支援
- くるみなどに多く含まれる「ALA」の血中濃度が高いほど、がん再発に対する不安感を抱く可能性が低いことが判明
- がんサバイバーへの偏見をなくし、恋愛・結婚をサポートする大学生向け教育プログラムを開発
- がんサバイバーには次のステージとして、ほかのサバイバーや医療者を支える役割を担ってほしい
カテゴリー家族と社会のがん闘病サポート, がん患者さんの支援・サービス
関連記事
※掲載している情報は、記事公開時点のものです。





