- 再発転移がん治療情報
- QOLを維持するために
- 副作用対策・痛み・辛さの緩和
- 【特集記事】注目が高まる、がん患者さんの「妊孕性温存」
【特集記事】注目が高まる、がん患者さんの「妊孕性温存」
目次
がん患者の「妊孕性」とその「温存」への関心が高まっている理由
「妊孕性(にんようせい)」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、「お子さまを授かるための力」のことを言います。実はがん治療などの医療によって、この妊孕性を失うことがあります。「妊孕性の温存」とは、このように病気の治療によって将来妊娠の可能性が消失しないように生殖能力を温存するという考え方です。
では、なぜ近年、若いがん患者さんの「妊孕性」が注目されるようになったのでしょうか? 大きな理由は3つあります。
1つ目は、がん全般の治療成績が良くなっているということです。つまり、がんを克服した人が増えて、がん治療後のQOL(生活の質)の向上にも関心が高まりました。そのQOLの1つが「妊孕性の温存」なのです。
2つ目は、これまでのがん患者さんの中には、がん治療によって「妊孕性」を失うことを知らないケースが多々あったことです。がん治療の内容によっては卵巣や精巣などの性腺機能不全を生じたり、手術で子宮・卵巣・精巣など生殖臓器を喪失したりするので、治療後に妊娠・出産することが難しくなる場合があります。こうした治療の影響を医療者側が患者さんに的確に伝えていなかった場合もあるでしょうし、患者さんが未成年の場合にはご両親がそうした生殖に関わる情報をブロックしてしまうこともあるのかもしれません。
事情はさまざまですが、妊娠する力を治療で失うことを知らないがん患者さんが現実にいらっしゃいます。治療が終わり、がんに打ち勝ったところでやっと未来に目を向けられるようになり、妊娠・出産を望む。ところがそのときに初めて妊娠する力を失ってしまったことを知り、愕然とする。このようなケースも少なくありません。
がんに打ち勝ったことは嬉しいことですが、特に20代、30代の若い方々にとっては、これからの人生を考え始めたときにいきなり「妊娠・出産することが出来ない」と宣告されるのは大きな打撃です。
こうしたがん治療に伴う「妊孕性」の解決につながるのが、生殖医療いわゆる不妊治療技術の発達で、これが3つ目の理由です。近年、がんの治療を始める前に「妊孕性」についてきちんとがん患者さんに情報提供しようという動きから始まって、温存できる生殖医療技術があるならその力を患者さんのQOL向上のために役立てようという取り組みが始まりました。
がん治療が「妊孕性」に及ぼす影響と事前の温存方法
抗がん剤や放射線治療は、男性にも女性にもその「妊孕性」に影響を及ぼすことがあります。男性の場合には、無精子症や性機能障害などが生じることがあります。この対策として従来から、がん治療前の精子凍結保存が行われてきました。抗がん剤治療後の無精子症に対しては顕微鏡を使った手術で精子を採取して妊娠に至った例もありますが、抗がん剤によるDNA損傷などの影響を考慮すると事前の精子凍結保存が推奨されます。
女性の場合、卵巣機能にダメージを受けて卵子数の減少や消失が起こります。また、年齢や抗がん剤の種類や投与量によっては20~100%の確率で早発閉経になることが知られています。女性の患者さんに対する「妊孕性の温存」の方法としては、「卵子凍結」「受精卵凍結」そして最近行われるようになった「卵巣組織凍結」の3つの方法があります。
「卵子凍結」は卵子を採取して凍結保存するもので、がん治療後に妊娠・出産が可能になった時点で解凍して体外受精を行い、受精卵を患者さんに移植します。米国臨床腫瘍学会(ASCO)によるとすでに世界で1000人以上の出産例があり、治療として確立されたと言ってもいいでしょう。
しかし卵巣がんの患者さんには適用が難しい場合があります。卵子を卵巣から採取することを採卵というのですが、腟から子宮に細長い針を入れて行うこの採卵によって、卵巣がんをお腹の中にばらまいてしまうことによるがん転移(腹膜播種)のおそれがあるからです。また、血液のがんの場合も、感染、出血が起こりやすいので、適用が難しい場合もあります。
「受精卵凍結」は、体外受精や顕微授精で受精・発育した受精卵を凍結保存する方法で、がん治療後に妊娠・出産が可能になった時点で解凍して患者さんに移植します。これは一般的な不妊治療と同じです。
「卵子凍結」と「受精卵凍結」は、一般的には薬剤によって卵胞を育てる必要があるので、がん治療開始までに時間的余裕があることが条件です。なぜなら、がん患者さんの「妊孕性の温存」では、がん治療が優先されるからです。「妊孕性の温存」のためにがん治療を遅らせることがあってはなりません。
「卵巣組織凍結」は、腹腔鏡で卵巣組織を採取して凍結保存しておき、がん治療後、患者さんの状態が妊娠・出産が可能になった時点で卵巣組織を患者さん自身に再び移植するものです。治療としてはまだ研究段階のものですが、2015年の報告では全世界で60例の出産例がありました。
がん治療後の「妊孕性」はまず精査を
理想はがん治療前に前述のような「妊孕性の温存」を行うことですが、がん治療を終えてからようやく家族計画を考えられるようになるのが現実でしょう。
すでにがんの治療を終えた女性の患者さんで妊娠・出産を望む場合には、必ずがん治療の担当医に家族計画の相談をして、ゴーサインが出たら、私たちのような生殖医療の専門家やこの分野に詳しい医師がいる施設で「妊孕性」の精査をしてください。男性の場合は泌尿器科でも精査が可能だと思います。
その際には、どのようながん治療を受けたのかという具体的な情報があると役立ちます。女性も男性も使用した抗がん剤に関する情報は重要です。特に女性の場合、抗がん剤の投与開始と共に生理が止まることはよくあることですが、なかには卵巣機能が低下して生理が戻らず、そのまま早発閉経になってしまうことがあるからです。
卵巣機能低下を引き起こす可能性のある代表的な抗がん剤は、シクロホスファミドに代表されるアルキル化剤が知られています。年齢にもよりますが、この薬剤をどれだけ投与したかが卵巣機能低下要因の1つとして考えられています。
下に「化学療法薬による性腺に対するリスク分類」の簡単な表を掲載しましたが、より詳しい情報については「特定非営利活動法人日本がん・生殖医療学会」のサイトにアクセスしてみてください。
卵巣の機能が低下し、若くして閉経するということは、排卵が起こらない状態になっているということです。しかし、まだ卵巣の中に卵子が残っている場合があります。そういう場合には薬剤によって排卵を促して採卵し、体外受精をすれば、閉経後の子宮でも受精卵を着床させることができる可能性があります。
逆に生理があっても無排卵ということもあります。このように生理の有無だけでは卵巣機能を評価できませんし、もともと卵巣の状態は病気の有無以前に個人差があるので、精査が必要なのです。
医療技術は常に進化しているので、今後がん治療前の「妊孕性の温存」や治療後の不妊治療成績も向上していくでしょう。しかし、課題もあります。がんという病気の治療に伴う生殖医療ではありますが、その費用は通常の不妊治療と同じ扱いなので経済的負担があります。
さらに、妊孕性温存の場合には不妊治療の助成金の対象外になっているため、患者さんの経済的な負担が非常に大きいのが現状です。滋賀県のように若いがん患者さんに対して、妊孕性温存治療の費用の一部を助成する自治体もありますが、まだまだごく一部と言えます。

出典:母子保健情報 第66号「悪性腫瘍と妊孕性温存について」 P29掲載表1より
がん患者さんの「妊孕性の温存」における今後の課題
医療者と患者さんにとって、がんに打ち勝つことが優先課題です。そのため、これまではがん治療による「妊孕性」の消失には目をつぶらざるを得ませんでした。私にも忘れられない体験があります。
今から十数年前の研修医時代に担当した患者さんは、妊娠中に卵巣腫瘍の手術を行い、卵巣がんが判明しました。その患者さんは赤ちゃんをあきらめ、反対側の卵巣と子宮切除の追加手術を受けました。現在の医療水準に照らし合わせても、当時の治療は患者さんの命を救うために賢明な判断であり、適切な治療だったと言えます。
しかし、その患者さんは赤ちゃんも、そしてその後の妊娠の可能性も失うことになりました。患者さんに対して医師としてもっと何か手立てはないのかと苦悩したことが思い出されます。その後、聖マリアンナ医科大学に転じ、生殖医療センターでがん患者さんの「妊孕性の温存」に携わるようになりました。
現在、本邦ではいわゆるホストマザーは倫理面から認可されておりませんが、イギリスやアメリカなどであったならば、今ならあの患者さんには受精卵凍結保存などの治療が適用できたのではないかと思います。
がん患者さんに知っておいてほしいこと
 これからがんの治療を受ける患者さんは、がんと告知されただけでも気が動転しているところに、将来の家族計画のことまで考えられないという方が多いでしょう。
これからがんの治療を受ける患者さんは、がんと告知されただけでも気が動転しているところに、将来の家族計画のことまで考えられないという方が多いでしょう。
しかし、将来的にお子様が欲しいと考えているならば、がん治療前にそのことを主治医に伝えておくことが重要です。もしもその医師が「妊孕性温存」についてあまり詳しくない場合には、私たちのような専門家や、この分野に詳しい医師がいる施設に紹介してもらうとよいでしょう。
また、生殖医療の専門施設を受診する際には、がん治療の担当医からのお手紙(紹介状)を持参することが望まれます。なぜならば、がんの患者さんの場合は、あくまでがんの治療が優先であり、がん治療の担当医と生殖医療の担当医の連携が必要だからです。
将来の妊娠・出産を希望して受診したがん患者さんのなかに、「がん治療の担当医から許可が出た」とおっしゃられていても、実際に連絡をしてみると担当医からはまだゴーサインが出せる状態ではなかった、という事例もありました。
妊孕性温存治療のためにがんの治療の開始を遅らせたり、将来の妊娠・出産を希望するためにがん治療を中断したりするようなことはすべきではありません。がん医療も生殖医療も、患者さんを中心に連携し、がんに立ち向かう患者さんを応援していきたいと思います。信頼して、相談してください。それが患者さんへのお願いです。
一方、私たち医療者側にもまだまだ課題があります。がん医療と生殖医療の連携もその1つですし、患者さんやその家族に適切な情報提供や精神的なサポートを行える支援体制が不可欠だと言えます。聖マリアンナ医科大学病院では生殖医療センターと乳腺・内分泌外科の連携で、乳がん患者さんに対する「妊孕性温存」が行われています。
また、小児科との連携では小児患者の将来を見据えた「妊孕性温存」への取り組みも始まりました。「妊孕性温存」は、がんに打ち勝った後の患者さんが得る「人生の選択肢の温存」と言い換えてもいいのかもしれません。
取材にご協力いただいたドクター
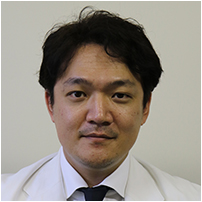
高江 正道 先生
聖マリアンナ医科大学 産婦人科学講師
カテゴリーQOLを維持するために, 副作用対策・痛み・辛さの緩和
タグ2016年8月
関連記事
※掲載している情報は、記事公開時点のものです。




